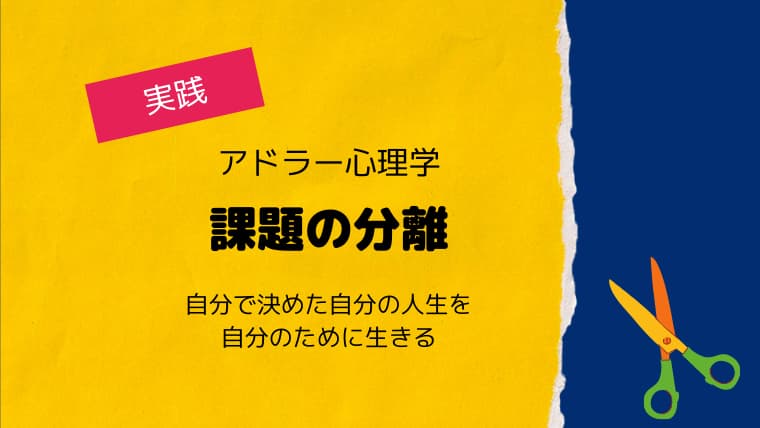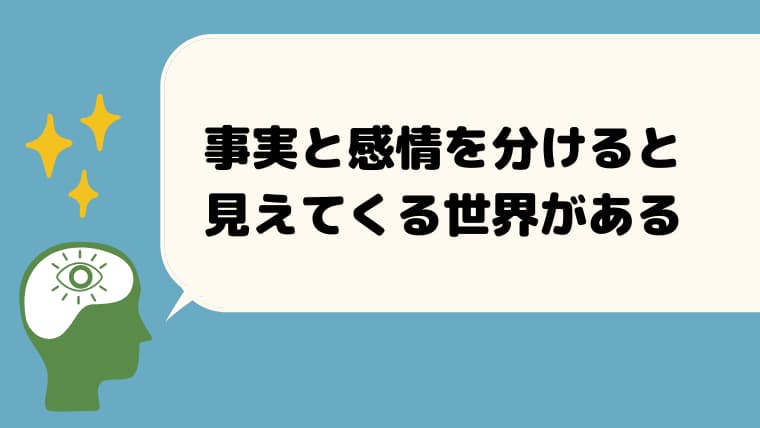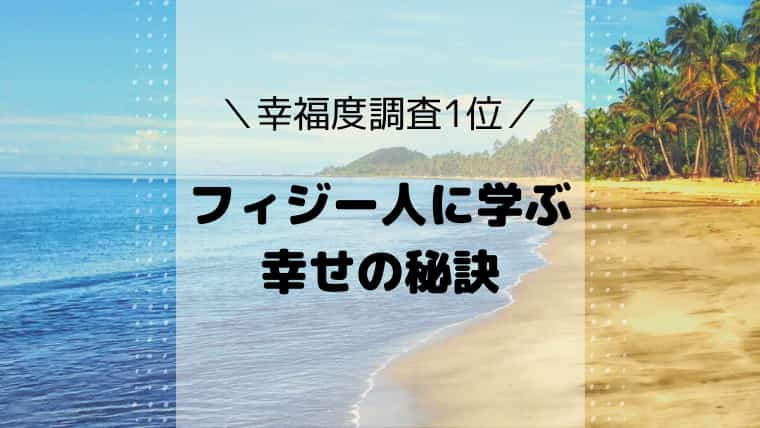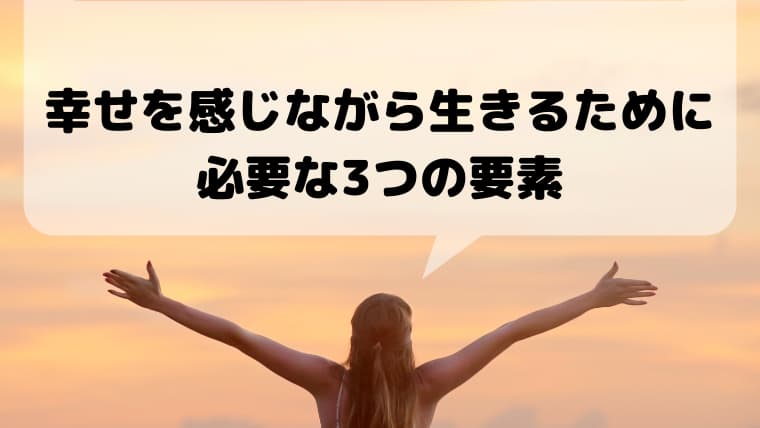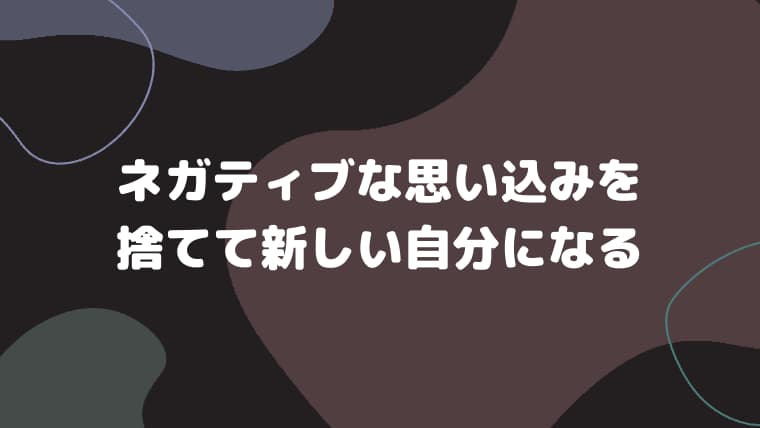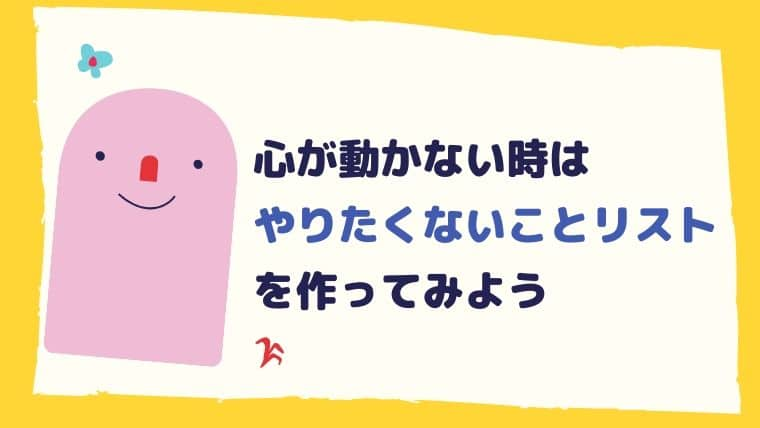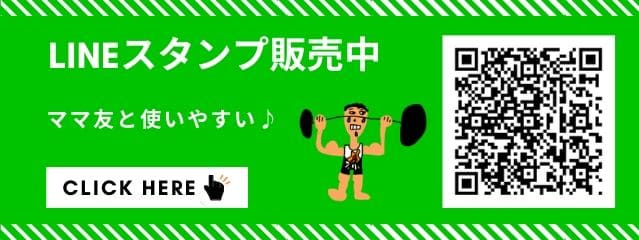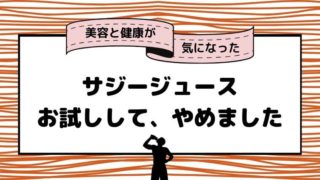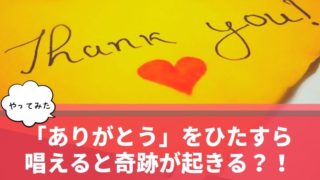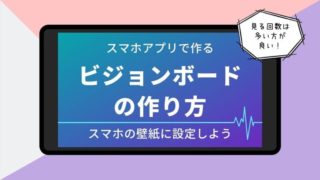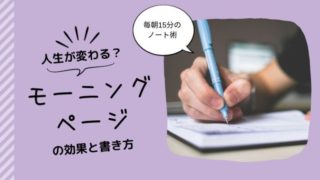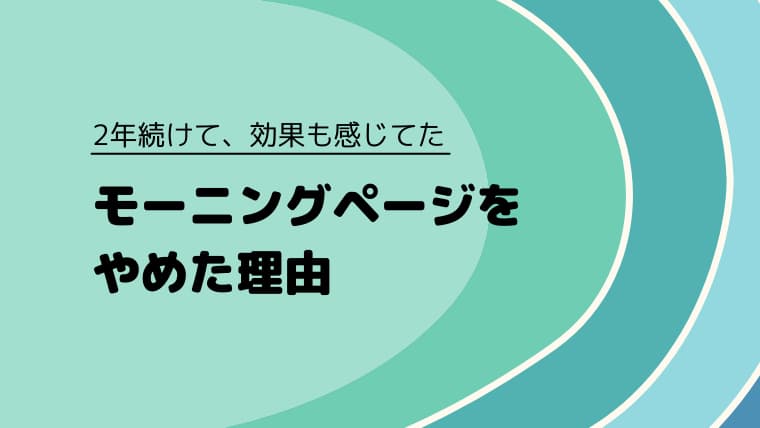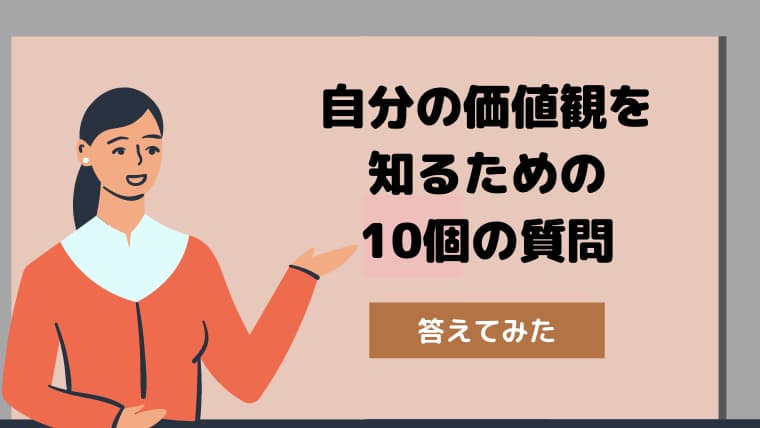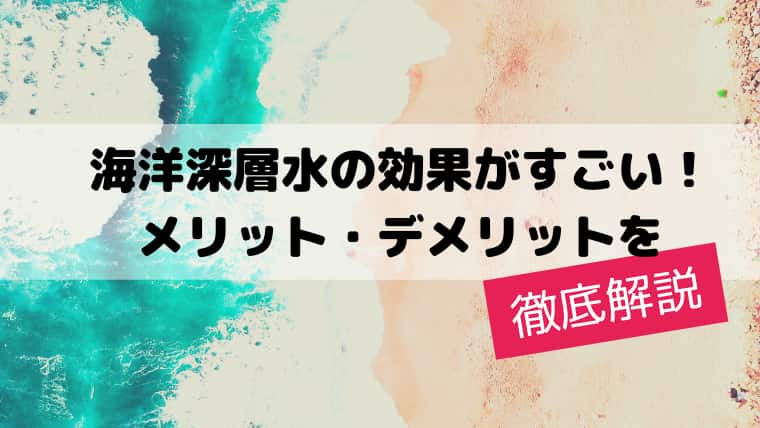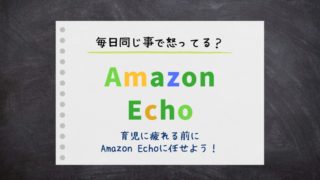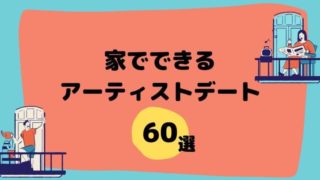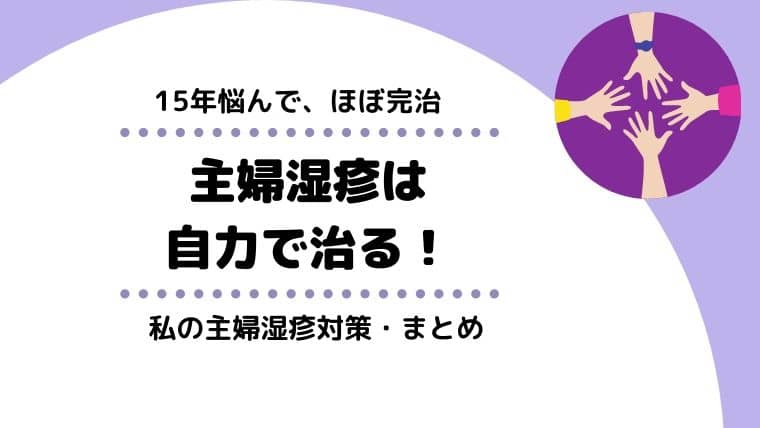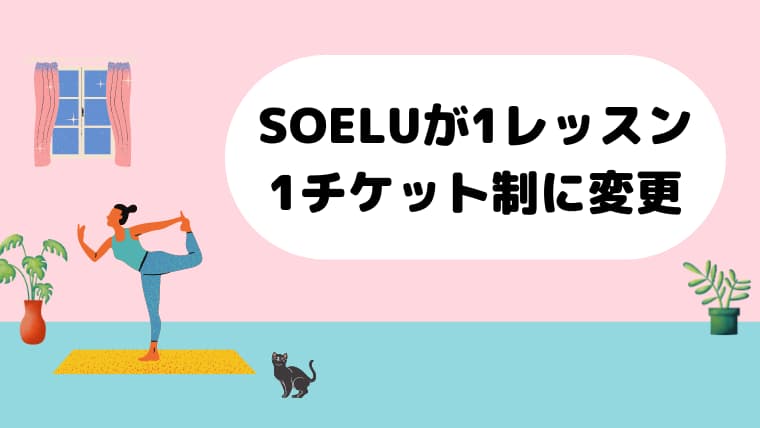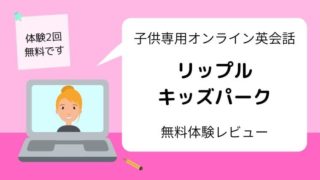「課題の分離」という言葉を知っていますか?
「課題の分離」とはアドラー心理学の重要な考えの1つで、「自分がコントロールできる事(自分の課題)と自分がコントロールできない事(他人の課題)を分けて考えましょう」というものです。
アドラー心理学では「すべての悩みは対人関係の中にある」と考えていて、「課題の分離」が出来れば悩みがなくなるというのです。
この記事では、
- 課題の分離とはなに?
- 課題の分離を実践するとなぜ悩みがなくなるのか?
- 課題の分離を実践するためのポイント
- 私の悩みを元に、課題の分離を実践してみた
について書いてあります。
課題の分離とは

私は、「課題の分離」という言葉を「嫌われる勇気」という本で知りました。
「アドラーの教えで俺のひねくれた性格や深い悩みを解決してみろ!」と吠える青年と哲人の対話形式でアドラー心理学を分かりやすく学べます。
自分の常識を根底から崩されるような、とぉぉっても良い本なのですが、「対話形式」なので文字では読みづらさを感じる人も多くいるみたいです。
私はAudibleで聴いたのですんなり入ってきたので、これから買う人にはAudibleをおすすめします↓
*今なら30日の無料体験が2か月に延長中です
*毎月、本を1冊+ボーナスタイトル1冊を無料で聴くことができます
課題の分離が出来ていない例としては、例えばこんな事になります。
- 子供が勉強をしないからヤキモキする
- 私ばかりがいつも家事をやっているとモヤモヤする
- 上司が仕事ができないとイライラする
よくある感じですよね。
私達は、他人に勝手に「こうあるべき」と期待をします。
それに反していると、勝手にヤキモキしたり、モヤモヤしたり、イライラしたりしています。
他人が自分の思うように動いてくれないという事に、ストレスを感じてしまうのです。
ここで、「嫌われる勇気」の本にもあった、「子供が勉強をしないからヤキモキする」という例で「課題の分離」をしてみます。
【子供の課題】勉強をするかしないか決める
子供が勉強をするかどうかは子供の課題で、親が子供の替わりび勉強もできないし、どうにか出来る事ではありません。
塾に通わせたり、家庭教師をつけて勉強をさせても、無理矢理やらされた勉強では、子供は「やらされている」と感じてしまいます。
親が「勉強しろ」というのは、子供の課題に踏み込む事になり、子供との衝突は逃れられなくなります。
【親の課題】見守る
子供の「勉強する・しない」の課題について、親が働きかけられることは、多くありません。
「今日、学校で勉強したことを聞く」「勉強しないとどうなるのかを伝える」「勉強したくなった時は援助するよと伝える」くらいで、基本見守る事のみです。
この行動で子供が変わるかどうかは分からないけれど、それは子供の課題だからどうしようもない、とアドラー心理学では考えます。
子供の意図に反して「親の求める事」を強要しても、反発しか得られません。
「他人は、自分の期待を満たすためにいるのではない」と認めることが大切です。
他人の課題を抱え込むと、自分が自分の人生を生きることが出来なくなってしまうのです。
課題の分離をするとなぜ悩みがなくなるのか

アドラー心理学では、「すべての悩みは対人関係の中にある」と考えます。
孤独を感じるのも、自分の容姿に悩むのも、収入が少ない事も、「比べる誰か」や「思い焦がれる誰か」がいるからある悩みです。
「幸せになりたい」などという個人的な悩みですら、他者と比較して出てくる悩みです。
宇宙にたった1人で、「他者」という存在が全くなければ、気にする事がありません。
人と人との結びつきは、自分の思い通りにはいかない事があり、それがあるから人は悩むのです。
「課題の分離」を実践すると、人間関係の悩みが解決する、つまりすべての悩みが解決する、とアドラー心理学では考えるのです。
課題の分離を実践するためのポイント
ではここで、課題の分離を実践するためのポイントを説明します。
- 課題の責任を持つのは誰かを考える
- 自分の課題にだけ向き合う
- 他者の課題に介入しない
では1つずつ説明します。
【ポイント①】この課題の責任を持つのは誰かを考える

「この課題をやって(またはやらなくて)、最終的に責任を負うのは誰か」を考えると、簡単に自分の課題と他者の課題を見分けることができます。
勉強をしない子供の問題だったら、勉強をしなくて困るのは子供。勉強をするかしないか決めるのは子供。
家事を1人でやっている問題だったら、手伝わなくて困るのは将来困るのは子供、家事を終わらせないと困るのは母親。手伝うかどうか決めるのは子供。
仕事が出来ない上司の問題は、仕事が出来なくて評価が悪くなるのは上司、仕事が出来ない上司のツケが回ってきて困るのは私。
こんな感じで、問題についてじっくりとどこが自分の課題で、どこが他者の課題なのかを考えていきます。
【ポイント②】自分の課題にだけ向き合う

自分の課題が見えてきたら、自分の課題だけに向き合います。
自分の課題に対して出来る行動の中で、最善と思うモノを選び行動します。
自分の取った行動に対して、人がどう思い、どう評価するかは「他者の課題」なので、気にする事はありません。
人から認められることを求めて、人の評価ばかり気にしていると、他人の人生を生きているという事になります。
自分が一生懸命自分の人生を生きずに、誰が自分の人生を生きてくれるでしょうか?
大切なのは、「自分がこれからどうしていくか」だけです。
紙に書き出すと取るべき行動が見えてくるよ↓
【ポイント③】他者の課題に介入しない

とは言え、勉強をしない子供、お手伝いをしない子供を前にして、何か口を出したくなりますよね。
でも、グッとこらえてください。
他者が他者の課題について、どういう風にするか決めた時、それはその人にとって最善の道だからです。
難しいのは、他者の選択を「信じる」という事です。
もちろん必要ならば援助もするし、話し合いはして、見捨てることはしません。
でも、基本は「この人は自分で課題を解決できる」と信じるのです。
自分が起こした行動で、他者がその想いに応えるかどうかは、他者の課題です。
あくまでも、自分の課題だけに集中して、他者の課題にまで介入しないように注意しましょう。
課題の分離を実践してみた

という事で、私の抱える「ズボラ問題」で課題の分離をしてみます。
(↑のイメージ画像だけはさわやかにしてみました)
私の悩みはいつものこれです。
部屋が汚くて夫に怒られた
怒られるたびに、自分のポンコツ具合に自己嫌悪してしまうのですが…。
まず、夫の欲求「夫が帰ってくるときには部屋をキレイな状態」が自分の目標になるかどうかを考えます。
ここで「夫のため」とか「自分が夫から認められるため」と考えると、他者の軸で生きていることになり、自分の幸せにはつながりません。
ということで、課題を分離してみます。
- 夫が帰ってくる前に部屋の掃除をしたい→私の課題
- 夕食前に子供達が部屋を片付けさせたい→子供の課題
- 夫が私を評価する→夫の課題
部屋を片付けたからと言って、夫が私を評価するかどうかは夫の課題なので気にする事はできません。
私は承認欲求の塊なので、明確な評価が欲しい所ですが、ここは「自分が夕食前までに部屋を片付けたいからやるんだ」と思う事にします。
子供達が部屋を片付けるかどうかは、子供の課題なので、無理強いすることは出来ません。
子供にガミガミ「部屋を片付けろ」というのは、子供の課題に土足で踏み込む行為で、良好な人間関係を築くことは出来ません。
私が出来ることは、「部屋を片付けないとどうなるかを説明する」「やるべきことを確認する」「やりたくなる仕組みを作る」「一緒にやる」くらいでしょうか?
結局私が1人で片づけをする事になりそうな気がしますが、アドラー心理学ではこれを「貢献感」で片付けます。
「誰からも認められないけれど、私は正しい事をして、誰かの役に立った」という貢献感が幸せを感じるためには大切なのです。
私が夫からの評価を求めるのは、「評価をもらえるからやる」となって、他人のために生きているという事になります。
「私が夕食前までに部屋を片付けようと決めて、片付けた。私、最高!すごいじゃん」と自己満足すればいいらしいです。
【まとめ】課題の分離を実践してみて

この記事では、アドラー心理学の「課題の分離」について紹介しました。
課題の分離で大切な事は、「自分で決めた自分の人生を、自分のために生きる」という事です。
そして、もちろん「他者が自分の人生を自分で決めて、その人自身のために生きる」ことも尊重しなくてはいけません。
アドラー心理学では、子供と言えども1人の優れた人間として尊重します。
親は「上の存在」ではなく、早く生まれた「前を進む存在」なだけです。
自分の目標に向かって、他人を動かそうとするとき、たくさんのコミュニケーションが必要になります。
1人の人間同士として、対等な立場で話し合い、風通しの良い人間関係を構築できれば、自ずと人間関係の悩みも減ってくるでしょう。
ただ、私の場合、子供に対しての課題の分離は大分出来ていますが、夫への承認欲求を捨てる事がなかなか出来ていません。
夫は横の存在であって、私の上にはいない。
そこら辺を自分の中に落とし込んでいくには、コミュニケーションが不足しているなぁと感じます。
以上、アドラー心理学の「課題の分離」についてでした。
まだまだアドラー心理学については学ぶべきところが多いので、シェアをしながら私自身も咀嚼していきたいと思います。