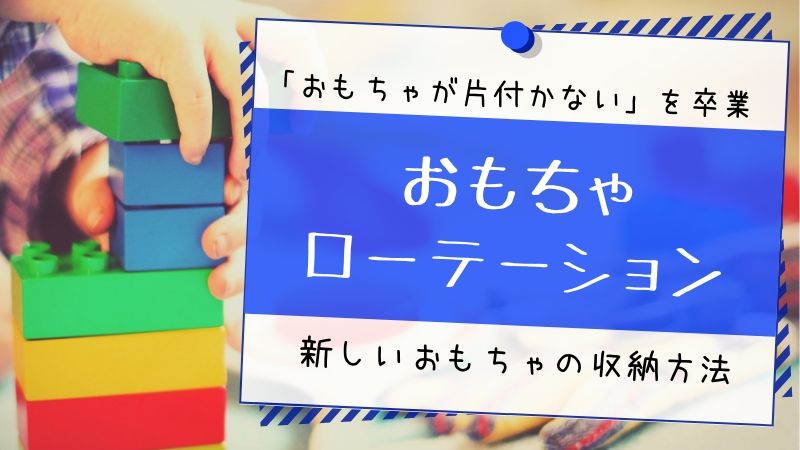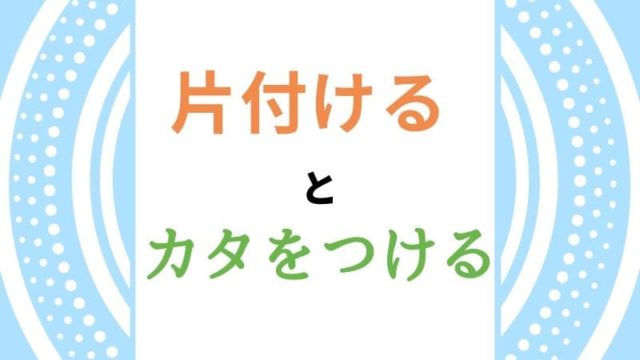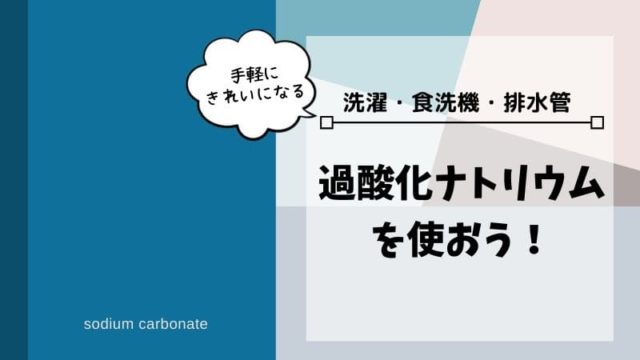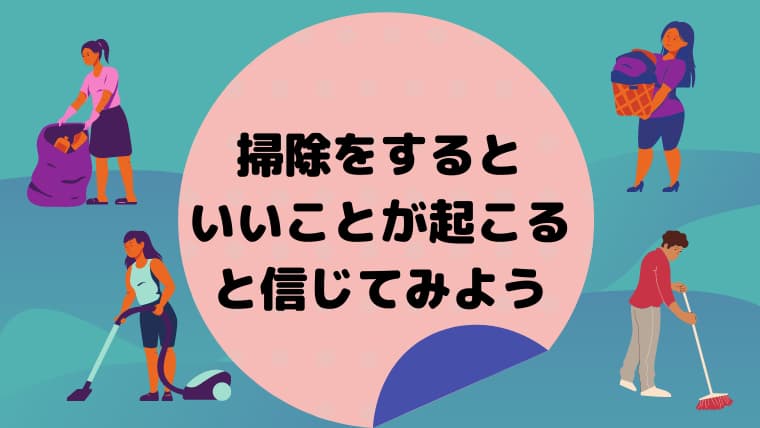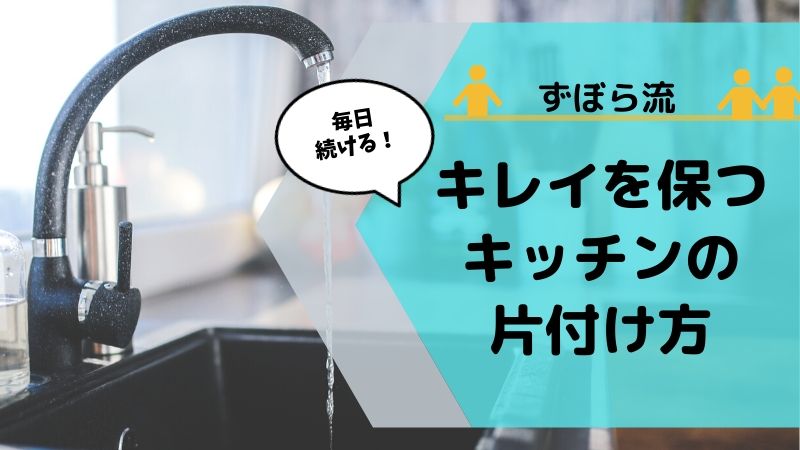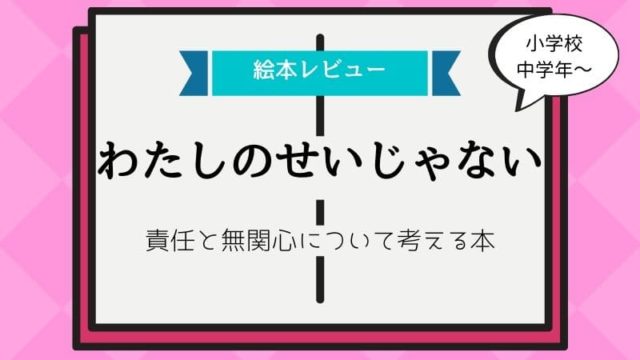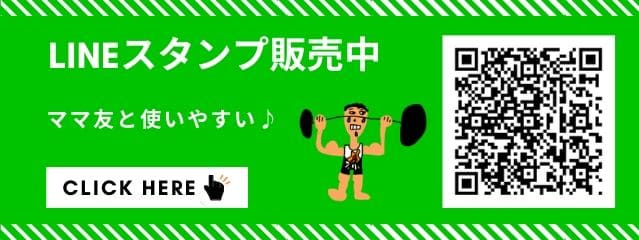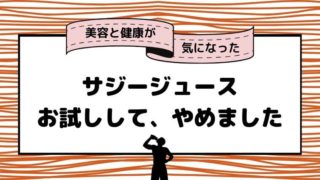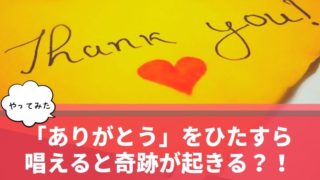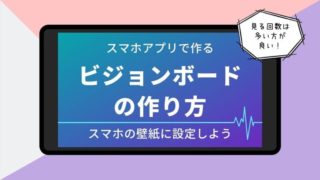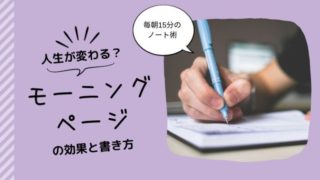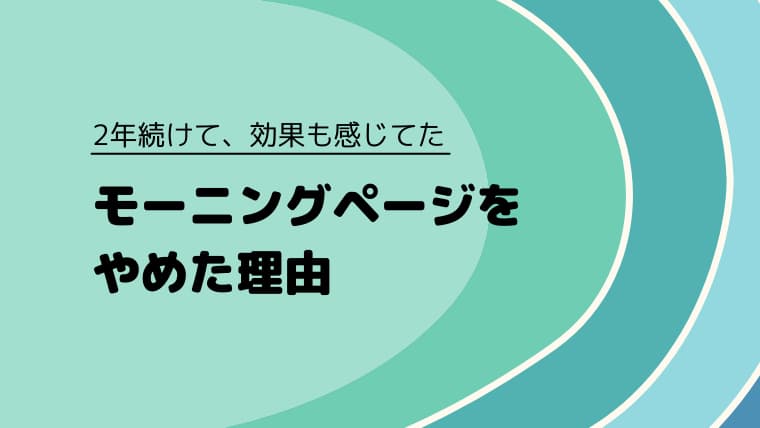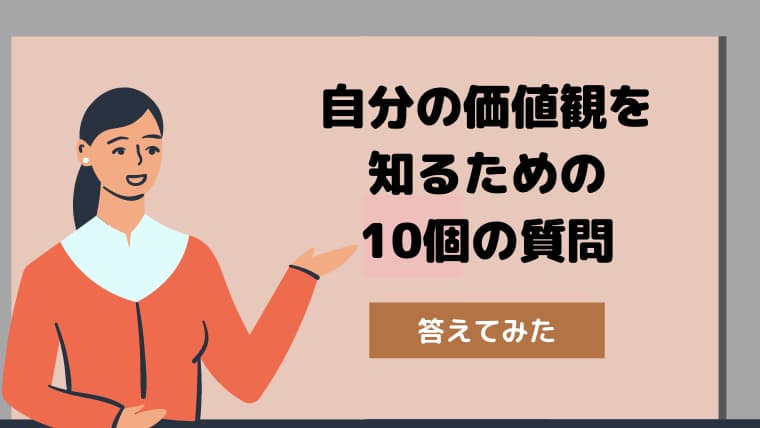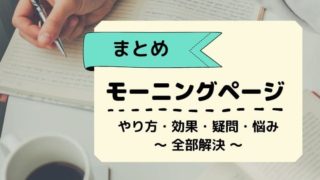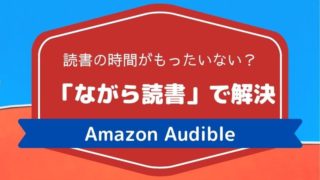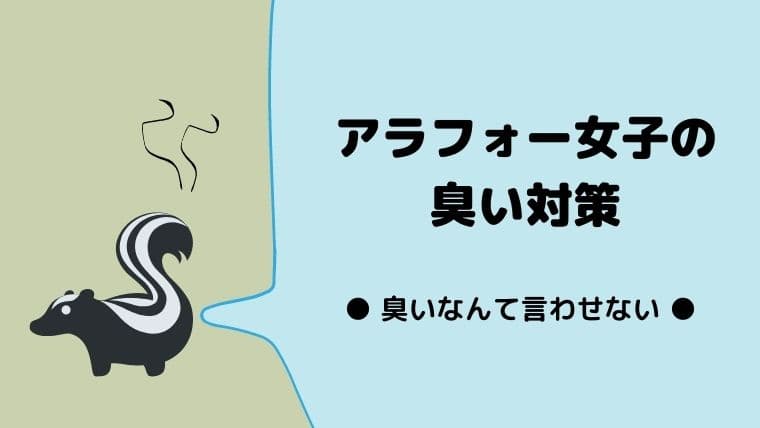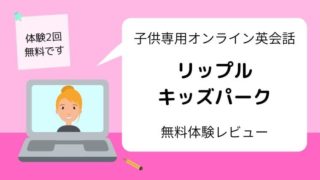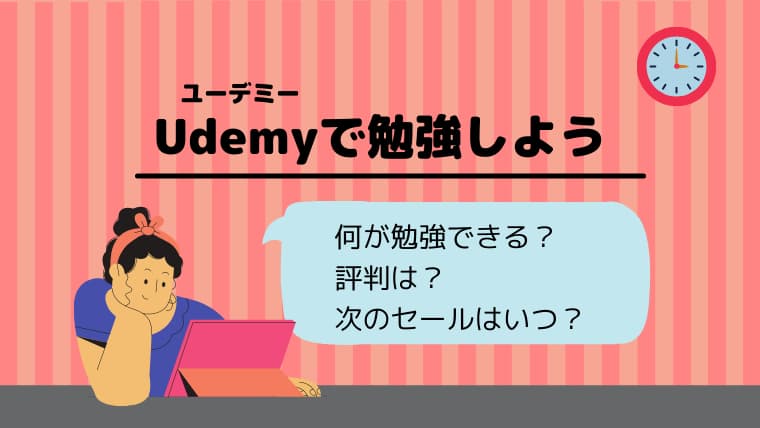リビングに散らばった子供のおもちゃを1日何度も片付けるうちにイライラしてきませんか?
子供達に「片付けなさい!」と言い続けて終わる毎日…疲れちゃいますよね。
でも、片付けがストレスフリーになるおもちゃの収納方法があるんです!
これは、子供達が小さかった時にウチで行っていた収納方法で、アメリカのお片付けポッドキャストでもよく紹介されている方法です。
この記事では、「おもちゃが多すぎて片付かない」とか「せっかく買ったおもちゃで全然遊んでくれない」思っている方におすすめの「おもちゃローテーション」というおもちゃの収納方法について説明します!
本当は、ウチのようなおもちゃが少ない家庭よりも、おもちゃが多くて片付かない家庭におすすめの収納方法です。
おもちゃが片付かないならローテーション収納がおすすめ

誕生日やクリスマスやレストランのお土産?など、子供達はおもちゃをもらう機会がたくさんありますよね。
祖父母が湯水のように与え続けたりして、部屋はおもちゃであふれていませんか?
おもちゃがたくさんあるから、集中して遊ぶかといったらそういうわけでもなく(涙)
「おもちゃが片付かない!」とイライラしてしまっているのではないでしょうか?
さて、「おもちゃローテーション」という言葉が突然でてきましたが、おもちゃローテーションとは、
洋服の衣替えのように、出しておくおもちゃを決めて期間ごとに回していこうという考え方に基づいた収納方法
おもちゃを数箱に分けて、 子供が遊べるおもちゃはその都度「1箱ずつ」にするシステム
のことです。
では、おもちゃを1箱ずつ出すとどのようなメリットがあるのでしょうか?
おもちゃローテーションのメリット
一般的におもちゃローテーションにはこんなメリットがあると言われています。
- おもちゃの片付けの時間が短縮される
- 子供がおもちゃを自分で片付けられるようになる
- 少ないおもちゃで満足する
- 遊ばないおもちゃを手放しやすくなる
- おもちゃが今までと違った方法で使われるようになる
1つずつ、詳しく説明しますね。
おもちゃの片付けの時間が短縮される

子供の遊び方を見ていると、1つの遊びからどんどん他のおもちゃに世界が広がっていきます。
そして、結局おもちゃを全部出してしまうという事になるのです。
根気強く「1つ遊んだら片付けてから次を出しなさい」と私たちは言い続けますよね。
いつかできるようになると信じて…!
でも、知り合いの保育士さんが言うには、これは子どもの自由な発想を妨げてしまうそうです。
もちろんそうですよね!
でも、おもちゃローテーションを使えば、そもそも出ているおもちゃが少ないので、片付けの時間が物理的に短縮されるんです。
子供が全部おもちゃを出してしまっても、たったの1箱分ですから!
子供がおもちゃを自分で片付けられるようになる

これ、多分、全国のママの願いです。
子供がおもちゃを片付けられない理由の1つに「どう片付けたらいいのか分からない」と言うのがあります。
そのために保育園などでは写真を貼ったりしているのを見たことがあると思います。
きっと家でも写真で何を入れるかを視覚化して、根気よく片付けを教えれば出来るようになるのかもしれません。
でも、いちいち写真を撮って、プリントアウトして、箱に貼って…って面倒くさくないですか?
おもちゃローテーションでは、おもちゃを全部出して散らかしても、箱の中に入れてしまえば「片付いた」となります。
だから、子供だけでもおもうちゃを片付けられるようになるのです!
娘の通っていた子育て支援センターが「箱に放り込む」式の収納をしていたので、うちの子供達でもすぐに出来るようになりました。
(声掛けと応援は必要ですが!←私はこれが苦手)。
少ないおもちゃで満足する

子供は毎日同じおもちゃを見ていると飽きてきてしまい、だんだん遊ばなくなってしまいます。
そうすると、そろそろ新しいおもちゃを買わないとなぁという気分になりますよね。
おもちゃローテーションを導入することで、毎日見るおもちゃは少量に限られます。
飽きたころに新しいローテーションになると、子供達は新しいおもちゃが出てきたような気分になるのです。
これで、次々と新しいおもちゃを買わなくても良くなります。
遊ばないおもちゃを手放しやすくなる

もう絶対遊んでないのに「これもう使わない?」と子供に聞くと、「まだ使う!」と子供に言われることはありませんか?
おもちゃローテーションでは、出しているおもちゃが多くありません。
その中でも遊ばないおもちゃが出てきたら、それは手放す候補になります。
次のローテーションが来ても遊ばなかったら、捨ててしまっても子供は多分気が付かないでしょう。
おもちゃが今までと違った方法で使われるようになる

子供は沢山のおもちゃに囲まれていれば満足でよく遊ぶというわけではありません。
一通りの使い方しか考えずに次々とおもちゃに手を出して、つまらなくなって大人に助けを求めてきます。
子供も、大人がたくさんのガラクタに圧倒されて参ってしまうのと同じです。
おもちゃが許容量を超えてしまうと集中できずに疲れてしまうのです。
おもちゃローテーションでは出ているおもちゃが少ないので、子供達が1つ1つのおもちゃにより集中するようになります。
そうすると想像力を使って、今までとは全く別の使い方をするようになることがあります。
ただのペンに布を巻き付けてお姫様にしたり、椅子を倒してアスレチックを作ったり、ブランケットをテーブルに被せて秘密基地を作ったり、お鍋やボウルを使って楽器を作ったり…。
少ないおもちゃだからこそ想像力を生かして生まれた遊びがウチにはたくさんあります。
おもちゃローテーションの始め方
ではトイローテーションの始め方を説明します。
- 箱を用意する
- 壊れているおもちゃ、使わないおもちゃを捨てる
- おもちゃをカテゴリー分けをする
- 期間を決めて、1箱ずつ出す
- たまにアップデートする
そのまんまな気もしますが、詳しく説明しますね。
箱を用意する

どんな箱でもいいのですが、もし使わないおもちゃを隠しておく場所がないのなら、透明ではない箱にしましょう。
箱が透明だと、子供達におもちゃが見えてしまい、「あれ出して」「これ出して」となりかねません。
どのくらいの頻度でおもちゃをローテーションするかにもよるのですが、毎日ローテーションをするならば箱は7個必要です。
我が家は元々のおもちゃが少ないので、2軍のおもちゃを1〜2ヶ月ごとに入れ替える方式で2個にしました。
壊れているおもちゃ、使わないおもちゃを捨てる
新しいシステムを導入するのに、壊れていたり、遊び倒してもう使わなくなったおもちゃを入れる必要はありません。
もう遊ばなくなったおもちゃはここで外しましょう。
おもちゃをカテゴリー分けする
箱の中には、色々な種類のおもちゃを入れたいので、まずは持っているおもちゃをカテゴリー分けしてみましょう。
例えばこんなカテゴリーに分けてみましょう。
- ゲームとパズル
- お絵描き用品
- LEGOやブロックのようなメイキングトイ
- おままごと用のコスチュームやキッチンアイテム
- ぬいぐるみやお人形
- 動かす系の車や音楽を楽しむおもちゃ
- 絵本
同じカテゴリーにたくさんおもちゃがある場合は、この時点で年齢に合ったものだけを残し、他は人にあげても良いと思います。
絶対にいつも遊ぶ1軍おもちゃは箱に入れずに出しておきましょう(ウチの場合はLEGOとお絵描き道具)。
箱に入れるおもちゃが決まったら、各カテゴリーから少しずつ選び、箱に入れます。
我が家にはあまりキャラクターのおもちゃがないのですが、例えば戦隊モノのコスチュームがあって、同じ戦隊モノの人形があった場合は同じ箱に入れた方が無難です。
きっと、思い出して欲しがったりするので。
期間を決めて1箱ずつ出す
子供が説明してわかるような歳ならば、これからはおもちゃをローテーションすることを説明しましょう。
そしておもちゃの片付け方を説明します。
それぞれの箱に何が入っているかは秘密にしておきます。
嫌がれるかと思ったけれど、うちの子たちは意外と大丈夫でした。
最初の数回は、一緒におもちゃを片付けてあげると良いと思います。
たまにアップデートする
遊んでる最中に、他の箱にあるものを欲しがったら、私は出してあげていました。
何がトリガーになって、そのおもちゃを欲しがったのかを見極め、次からはその二つをペアにします。
遊ばないおもちゃは手放す候補にするか、もしかしたら年齢と合ってないのかも?などと観察します←この余裕が生まれます。
「おもちゃが片付かない」から卒業しよう!

そのうち子供達もどこにおもちゃを隠しているのか分かって、勝手に取り出すこともありましたが、そのたびに違うものを箱に入れていました。
部屋がおもちゃで溢れないようにするのが目的なので、必ずその1箱で遊ばないといけないと言うわけでもありません。
子供達にとっても、触れられない時間があると、自分にとって本当に必要なおもちゃが分かってくるようで、使わなくなったおもちゃをスムーズに手放せるようになりました。
おもちゃが片付かなくて泣きたくなる事が多い方には是非おもちゃローテーションを実践していただきたいです。
カテゴリー分けとか面倒だったら、ぶっちゃけ家にあるおもちゃを半分隠すだけでもいいです。
一日何度もおもちゃの片付けをしていると、本当泣きたくなるし、体力奪われるし、イライラしちゃうので、とにかくおもちゃの片付けから解放されましょう。